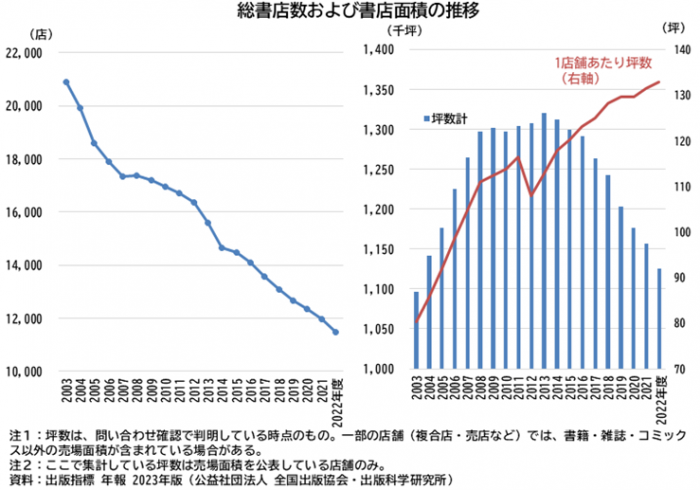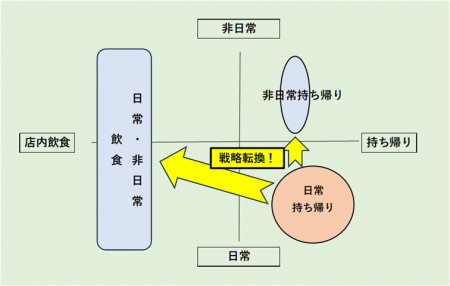アップデート
アップデート
■先週の土曜日(7/20)、関係している会社が、
著名な講師を招き、立派な会場を貸し切って
講演会を行いました。
第30回となる社員勉強会。一般の方も2千円で
聴講でき、大学生以下の方は無料ということで
学生さんも30名ほど参加し、大盛会となりました。
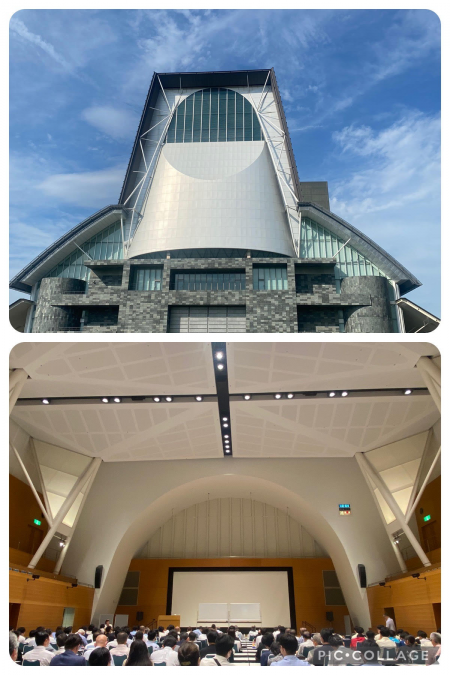
夕方から、都内に移動し、大学院時代の仲間たち
との旧交を温めました。
彼らは、多忙な経営者でありながら、社会人
大学院生として、経営学と、人としてのあり方を
学び直した人たちなので、強い好奇心と向上心を
持ちあわせています。
そんな彼らと話していて感じたことを共有します。
■明治の事業家で、松永安左エ門という人が
います。
「電力の鬼」といわれ、日本の電力事業の発展に
大きく寄与した人物です。
彼いわく
『経営人として成長したいなら、どんな経験を
積めば良いのでしょうか?』と問われて
『自分という人間と向き合う時間を長く確保する
ことが重要である。そのためには3つの「T」が
必要だ。
それは「投獄」「倒産」「大病」である』と。
■松下幸之助・稲盛和夫・孫正義。
誰もが知っている経営者ですが、彼らに共通
しているのは大病を経験していることです。
彼らが病を得て、自分と向き合ったことは多くの
本に書かれています。
しかし、私たち凡人は、「大病」や「倒産」
「投獄」など、どれも、経験したくないことです。
■通常、経営者は自分にとって、居心地が悪く
ない状況にあります。
(「大病」や「倒産」「投獄」などと比べて)
先にご紹介した大学院の仲間たちは、居心地の
悪い環境に身をおくことを、自ら選んだ人たち
です。
それは
・自分の年令や役職は考慮されない
・ちやほやされない
・厳しい指摘を受ける
・忙しい中、時間を作り勉強しなければならない
などなどです。
■そんな彼らと話していて、思い出した言葉が
<アップデート>です。
アップデートとは、本来、ソフトウェアや
アプリケーションを最新の状態に移行するための
作業を指しますが
近年は、人も自分自身を改善し、新しい知識や
スキルを獲得することも意味します。
■環境変化が激しい昨今、過去OKだったことが、
今ではNGあるいは、即逮捕、といったことが
数多くあります。たとえば・・・
・立ち小便
・飲酒運転
・学校での体罰
・飛行機内での喫煙
・職場でのプライバシー干渉
・休日出勤の奨励
・ゴミのポイ捨て
・電話帳の使用
・職場でのジェンダー差別
・書類の手書き
・男女の役割分担
・レジ袋の無料配布などなど、
数え上げたらキリがありません。
そして、これから、上記に掲げていない新たな
事柄がどんどん増えていきます。
■同様に、中小企業の場合、無自覚のうちに、
我が社の常識は、世間の非常識となっている
状況もよくみられます。
いつの間にか、時代に取り残されぬよう、人と
して、ビジネスパーソンとして、アップデート
すべく、せめて、
『自分という人間と向き合う時間を長く確保する』
という習慣強化をしようと、思いを新たにした
週末のイベントでした。
以上、最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
今日も、皆さまにとって、
最幸の一日になりますように。
日々是新 春木清隆
―――――――――――――――――――――
変化は避けられないが、成長は選択である。
ジョン・C・マックスウェル (牧師 1947年~ )
―――――――――――――――――――――