なぜ人は辞めるのか?時間と努力が実を結ぶ人財施策
■先週の週末は、ゆっくりと充電できました。
毎月恒例のお墓参り、振り返りとこれからの
諸準備。そして、大汗を流して心身を整える
ことができました。
お墓参りは、妻とともに、手をあわせてお参り
できることを心から感謝できる幸せな時間です。
■人手不足による、業務や経営への圧迫は、日を
追うごとにその厳しさを増してきています。東京
商工リサーチが9月8日に発表した2025年8月
の全国企業倒産状況の概要は以下のとおりです。
・倒産件数は805件。前年同月比で11.3%増加
・「人手不足」関連倒産は23件
・「人件費高騰」によるものが3倍に増加
今回は、私たち中小企業がこの状況に対応するた
めの方策について考えてみます。
■下表は2024年1月に『人手不足問題への対処』
と題して本欄でご紹介した際に使用しました。
ドラッカーの著した『明日を支配するもの―21
世紀のマネジメント革命』で述べられていること
を抽出し、筆者からみた実際にありがちな状態を
整理した上で、望ましい状態と打ち手を示したも
のです。
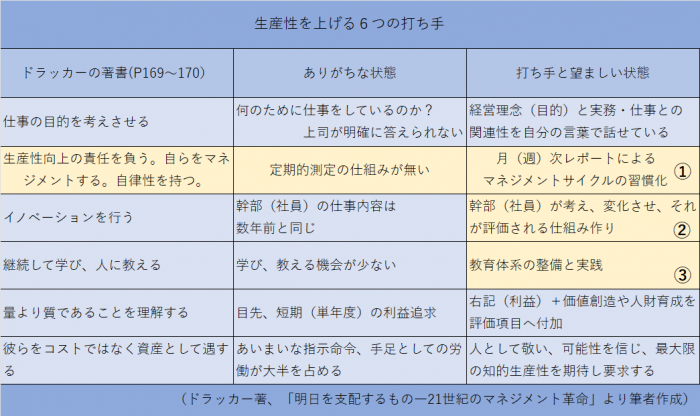
この表を作成した目的は、今働いてくれている人
たちはもとより、これから働いて欲しい人たちに
とって、魅力的な待遇の源泉となる粗利益を増大
し、生産性を上げるためでした。
■今回は、この基本思想をベースに
「採用後の人財定着」というテーマに焦点を
当てて考えていきます。
一般的な中小企業では、採用活動には多くの時間
労力、費用を費やしている一方で、せっかく採用
した人財の定着に向けた取り組みについては、そ
の比重が半分以下にとどまっているのが現状では
ないでしょうか。
■採用後の人財定着について、
重要となる指標が、(転職的)離職率です。
ご存じの方も多いと思いますが、離職率は以下の
数式で算出します。
期中離職者÷期首人員数
(転職的)としているのは、転居や定年など、
やむを得ない理由による者を離職者の中から
差し引いた数字を用いるからです。
■この離職率を全社~部門別~現場別で毎月測定
することが、先に示した表の黄色の網かけ部分、
<定期的測定の仕組みが無い<を<有る>に変化
させ、人財定着の第1歩になります。
その数字を月(週)次レポートにより、マネジメ
ントサイクルを定例化することをモニタリングと
いいます。(表①部分)
■モニタリングを続けていくと、数字は正直です
から、今まで漫然と「人が足りません」と言って
いた<真因>が明らかになってきます。
このプロセスで大切なことは幹部(社員)が考え
その<真因>を見つけ出すことです。(表②部分)
なぜなら、自分たちで見出した課題だからこそ、
その後の改善活動に本気で取り組むことができる
からです。
筆者の経験では、<真因>の改善で離職率は5%
以上改善できる可能性があります。
■<真因>ならびに、その改善内容は会社によっ
て異なりますが、
それが評価される仕組み作り(表②部分)と、
教育体系の整備と実践(表③部分)に
その対象範囲が、展開していくことは、各社共通
です。
ここまで、深刻化する人手不足への対処として、
私たち中小企業が、スグに取り組め、効果の出や
すい事例をご紹介しました。
この取り組みは、すぐに結果が出るものではなく
時間と継続的な努力を要します。
しかし、この地道な取り組みこそが、社員一人
ひとりを「人財」へと育て、評価や教育体制など
会社を支える強固な「仕組みづくり」へとつなが
る、会社全体を強くする着実な方法だと信じてい
ます。
以上、最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
今日も、皆さまにとって、
最幸の一日になりますように。
日々是新 春木清隆
―――――――――――――――――――――
「子曰、譬如爲山、未成一簣、止吾止也。」
「どんなにゆっくり進んでも構わない、止まりさえしなければ。」
孔子((思想家 紀元前551年 ~ 紀元前479年)
―――――――――――――――――――――
