中小企業が「人手不足」を乗り越える3層対策
■先週は、日曜日の伊豆高原での合宿研修に始ま
り、平日は、静岡県~兵庫県などで顧問業務を行
い、週末の土曜日には、湘南で30代の後継者の
方と合宿を行う一週間でした。
翌日の日曜日には、妻と一緒に映画『国宝』を鑑
賞しました。
同じ映画を二度観ることは滅多にありませんが、
観終わったあとに、上映時間と同じ3時間ほど、
妻と感想を語り合うことができ、とても楽しく
豊かな時間を過ごせました。

■11月9日の日経朝刊に「労働臨界」と題した
特集記事が掲載されていました。その内容は、
深刻な人手不足が日本の経済成長を大きく阻害し
ており、人手不足による機会損失額は年間16兆
円に達しているということでした。
日経新聞は16兆円とマクロの数字について解説
していますが、私たち中小企業にとっては、
「人手不足」とそれによる機会損失が大きな悩み
のタネです。
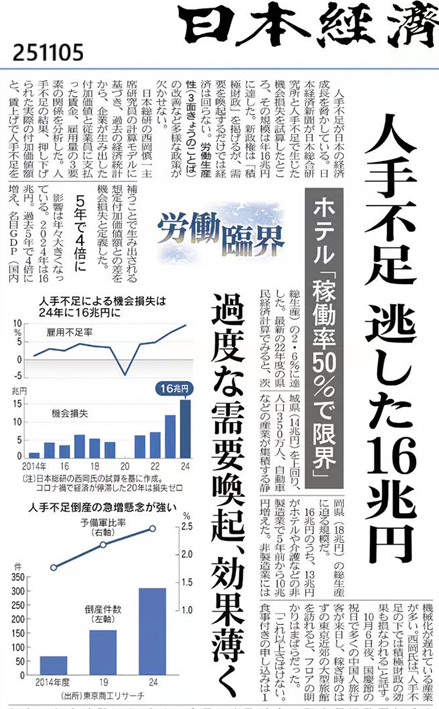
■実際、私たち中小企業が該当する従業員300人
未満の会社の求人倍率は6.5倍と、求職者一人に
対して、6.5社が採り合いをしている状況です。
求人倍率6.5倍ということは、求人を7回打てば
一人の採用が可能である。こととは違います。
現実は、諸条件の良い会社1~2社が人を採り続
け、以外の3~7社は採用ゼロが続くことを意味
します。
今回は、中小企業にとって実効性のある「人手不
足対策」を過去本欄で取り上げた内容をベースに
ご紹介してまいります。
■本欄の過去記事で、「人手不足対策」について
考察したものは下表のとおりです。
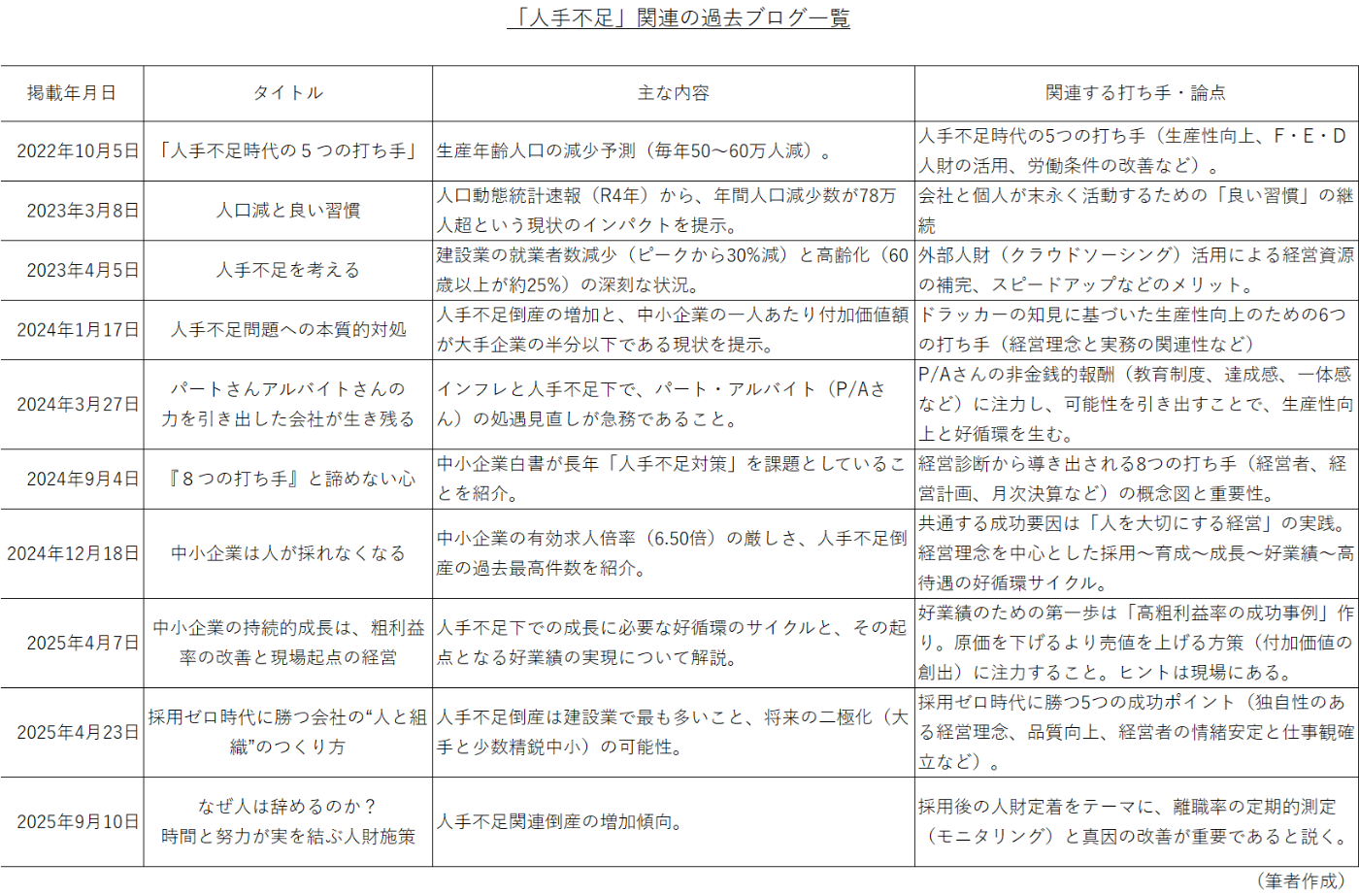
これらのブログでは、私たち中小企業が「働く人
に選ばれ」、持続的な成長をするための3つの層
と、それを貫く好循環サイクル(下図)について
述べています。

この好循環サイクルの中心にあるのは、経営理念
の理解・実践・浸透で、「人を大切にする経営」
です。
このサイクルでは、「採用」した人を「辞めない
ように育成」し、「成長」した人が「好業績」を
生み出し、「高待遇」につなげるサイクルを示し
ています。
■つぎに持続的な成長をするための3つの層は、
下図のように3層構造になっています。
3層はその重要度順に示しており、
第1層が、経営の土台となる「人手不足」時代を
乗り越えるための、経営者自身の覚悟と前提づく
り。
第2層が、高収益企業の必須要件となる収益力の
強化。
第3層が、継続的発展のための要件となる人財の
確保・定着について示しています。
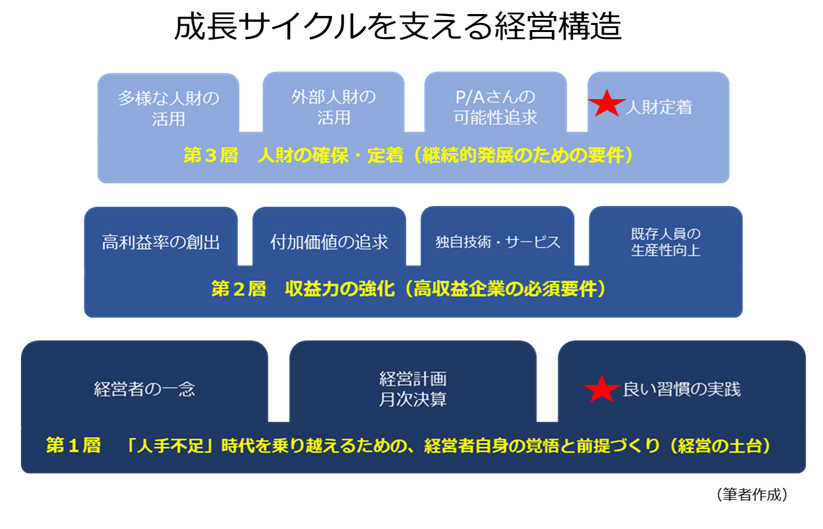
■各項目の詳細は、先にご紹介した以前の本欄で
述べていますが、ここで改めて★良い習慣の実践
と★人財定着について解説します。
★良い習慣の実践とは、5Sの徹底と、提供品質
のたゆまぬ向上、そして(経営)計画と実績の差
異分析です。
★人財定着は、離職率を全社・部門別で毎月測定
し、その真因を幹部が突き止め、改善することで
定着率を向上させる取り組みです。
■求人倍率6.5倍という採用環境は、中小企業に
とって待ったなしの危機で、人が採れずに廃業と
いう現実に直面していることを意味します。
この難局を乗り越える鍵は、
「経営理念の理解・実践・浸透」を中心とする
「人を大切にする経営」、すなわち好循環サイク
ルを回し続けることです。
「良い習慣」や「離職率の測定・改善」は経営者
の一念を要し、時間がかかりますが、継続すれば
必ず社員の成長となり、会社を強くする「仕組み
づくり」につながります。
この危機を「ピンチはチャンス」と捉え直し、
「働く人に選ばれる会社」を目指して、共に進ん
でいきましょう!
以上、最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
今日も、皆さまにとって、
最幸の一日になりますように。
日々是新 春木清隆
―――――――――――――――――――――
「組織は、人を惹きつけ、引き止められなければならない。彼らを認め、報い、動機づけられなければならない。」
ピーター・ドラッカー
(経営学者 1909~2005年)
―――――――――――――――――――――
