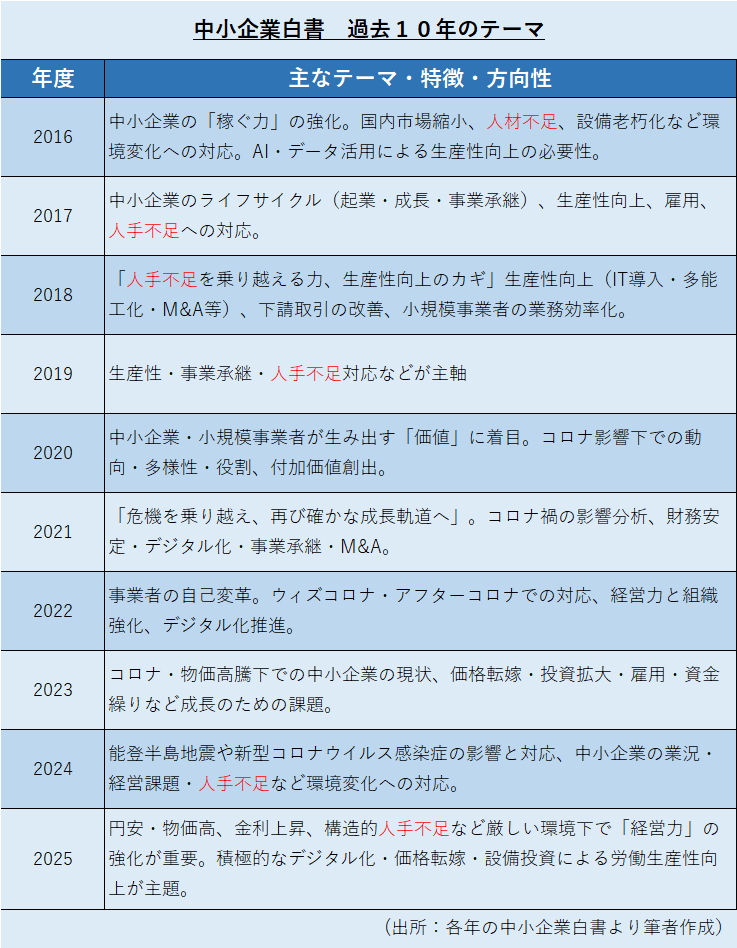『運』【読書メモ】
■今回は久しぶりに読書メモを共有します。
著者はドン・キホーテの創業者、安田隆夫氏です。
ドン・キホーテは、創業以来三十四期連続で
増収増益を成し遂げ、売上二兆円の日本を代表
する企業です。
おなじように連続して成長し続けている会社に
ユニクロとニトリがあります。
3社の共通点は、それぞれ小売・洋服屋・家具屋
と、どこにでもある業種であること、そして、
オーナー経営者であること。
また、安田隆夫氏は岐阜県大垣市出身。
ユニクロは山口県宇部市、ニトリは北海道札幌市
という地方都市での創業など、私たち中小企業と
の共通点が見いだせます。

(出所:各社IR資料より筆者作成)
日本の上場企業数は、約4,000社。
その中で、20年以上増収し続けている会社は
全体の0.5%の20社程度。
その中にこの3社は入っています。
■ドン・キホーテという屋号で小売業を展開する
会社の正式名称は株式会社パン・パシフィック・
インターナショナルホールディングスです。
(英語名:Pan Pacific International Holdings Corporation)
以下PPIHと表記します。
この業界はかつて、ダイエー(現イオングループ)、
ユニー(現PPIH傘下)など総合スーパーが
全盛を誇っていました。
それら大手企業が、そろって業績を下げる中で、
なぜPPIHだけが三十四期連続で増収増益を続け
ているのか?
また、SBIホールディングスの北尾吉孝氏が、
「経営書として、人生の指南書として、常に傍に
置いておきたい」とコメントしていること。
本書からその基本的な考え方などを知りたく読み
始めました。

■『運』という題名のこの本を読んで印象に
残ったことを3つ記します。
まず第1は、「楽観主義」です。
安田氏は、困難な状況に直面しても前向きな姿勢
を保つことが重要だと強調しています。
創業初期に廃業寸前まで追い込まれた際も、
「危機はいわば成長痛」と捉え、悲観せずに前向
きな気持ちで乗り越えたエピソードが紹介されて
いました。
この根拠なき自信のような「楽観主義」は、
松下幸之助はじめ多くの成功者も唱えています。
次に「挑戦する」ことです。
安田氏は、数多くの新業態開発に取り組んでいま
す。主幹業態であるドン・キホーテや海外業態の
DON DON DONKIなど、現在ある15の業態は
100の挑戦があったから、逆を言うと8割以上の
失敗があったからだと述べています。
この挑戦する姿勢はユニクロの創業者である柳井
正氏の著書『1勝9敗』でも同じ考え方が紹介
されていました。
3つ目は、「経営理念」の大切さです。
安田氏は、企業理念集『源流』を発行しています。
ここで「経営理念」を、未来永劫にわたり普遍的
かつ、絶対的な価値観として全従業員・役員に明
文化して示し、遵守を徹底しています。
そして、組織運営や人財育成、事業判断の根幹と
して機能させています。
「経営理念」の重要性については、ニトリの
創業者である似鳥昭雄氏はじめ、多くの経営者や
経営学者がその実践の重要度を唱えており、改め
て、再確認できました。
本のタイトルは『運』ですが、その内容は、
いわゆる「運まかせ」や「一か八かの奇抜な方法」
に頼るものではありません。
むしろ、経営の神様・松下幸之助や、古今東西の
思想家たちが説いてきた原理原則と深く通じる、
非常に本質的な内容でした。
■最後に本の中で印象深い言葉を列記します。
・運を良くする行為、悪くする行為は必ずある
・不運の時は下手に動かず、チャンスが巡ってき
たら一点突破でがむしゃらに突き進む
・もがき苦しみ、唸りながら考え抜いた先にしか
活路はない
・挑戦をやめた瞬間に運は落ちる
・無私の姿勢で従業員や顧客の幸せを第一に考える
以上、最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
今日も、皆さまにとって、
最幸の一日になりますように。
日々是新 春木清隆
――――――――――――――――――――
「無私で真正直」が盛運をもたらす
安田隆夫(ドン・キホーテ創業者 1949年~)
――――――――――――――――――――